




ウォルドルフ人形(Waldorf Doll)は、どこか懐かしく、素朴な魅力を持つ手作りの人形。
ポポちゃんやメルちゃんといった一般的なお世話人形とは異なり、シンプルで昔ながらの姿が特徴的です。
ですが、そのシンプルさこそが子どもの心を動かし、いきいきとした遊びの様子を見せてくれるのです。
 ちいくまちゃん
ちいくまちゃん見た目以上に深い意味が込められているんだな~。
この記事では、ウォルドルフ人形の魅力や手作りの方法、さらには購入できるお店について詳しくご紹介します。
 ちゃみ
ちゃみウォルドルフ人形を通じて、子どもの心に触れる素晴らしい時間をぜひ体験してみてくださいね。
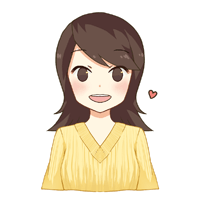
ベネッセ幼児教材公式アンバサダー/明治クラフトアンバサダー/Yahoo!をはじめとする各種メディアで執筆中/元教師
ウォルドルフ人形は、シュタイナー教育の思想を背景にドイツで生まれた抱き人形です。
シュタイナー教育を受けたスウェーデンのKarin Neuschutz(カーリン・ノイシュッツ)さんが、著書『LEK MED MJUKA DOCKOR―ぬいぐるみ人形とあそぼうー』の中で紹介したことから広く知られるようになりました。
日本へは、カーリンさんの著書を訳した『ウォルドルフ人形の本』で紹介されました。
本に登場する人形を、訳者の佐々木奈々子さんが「ウォルドルフ人形」と名づけています。
ウォルドルフとはドイツでシュタイナー学校として最初に開校した「ヴァルドルフ(ウォルドルフ)学校」のこと。
 ちゃみ
ちゃみ世界的には、「シュタイナー教育」よりも「ウォルドルフ教育」と呼ぶ方がなじみがあるのよね。
つまり、ウォルドルフ人形はシュタイナー教育の象徴ともいえる学校の名前を冠したスゴイ人形なんです。
それほどまでにシュタイナー教育の中でも、ウォルドルフ人形は大切にされているんですよ。
ウォルドルフ人形の特徴は以下のとおり。

一つ目の特徴は、遊ぶ子どもたちの想像力を刺激する見た目。
“小さなインクのしみ”と表現されるように、目や口がとても控えめな大きさです。顔の特徴がまったくない場合もあります。
 ちいくまちゃん
ちいくまちゃんわかるかわからないかくらい、小さいね~! なんで?
それは、子どもが自らの想像力を使って人形に働きかけることができるようにするためです。
シュタイナー教育の創始者であるルドルフ・シュタイナーは、幼い子どもの想像力を刺激し「内なる描写(想像力)」を養うために、子どものおもちゃは大部分が未定形であるべきだと提唱しました。
 娘
娘うれしそうにわらっているね!
子どもが人形に向き合っているとき、想像力が働きます。
あえて印象がない顔にすることで、楽しいときは笑ったり、悲しいときは泣いたりすることができるのです。
 ちゃみ
ちゃみ単純で素朴なほど想像力を働かせることができるというわけね。
そう、お店で売られている有名なお世話人形は大人にとっては良質なおもちゃに思えますよね。ですが表情が決まっていていつも同じ反応をします。
決まった反応を繰り返すだけの人形にはいずれ飽きが来てしまうんですね。
ウォルドルフ人形は素朴な表情だからこそ、多彩な反応を返してくれるのです。
子ども自身もうまく表せない気持ちを人形と共有することで、「心のお友達」や「仲間」といった存在ととらえるようになるんですよ。
幼児期に五感をたっぷり使った体験をすることは成長に不可欠。そういった体験ができるおもちゃを与えることはとても重要です。
ウォルドルフ人形は「感覚の赤ちゃん」としても知られているくらい、感覚を刺激するお人形です。
体は綿のジャージー素材で作られており、中には羊毛がしっかりと詰めこまれています。
これは子どもの肌の弾力に近づけるため。抱きしめた時にもあたたかみが伝わってきて、子どもが安心するんです。
しかも、長く抱くほど詰め物が温かくなるので、適度な重さと相まって実際の赤ちゃんを抱く感覚に似た感覚を得られるのです。
 ちゃみ
ちゃみ手足がぐにゃぐにゃしたところがない、しっかりとしたバランスなのが特徴ね!
材料はできるだけ天然のものが使われています。
色も自然そのままの色か、草木染で着色しています。これには、小さなうちから自然素材の良さを覚えてほしいという願いが込められています。
 ちゃみ
ちゃみ子どもにはできるだけ安心・安全なものを与えたいものね。
汚れたら洗えますし、やぶれたら繕えるところも良い点。
抱きしめると柔らかさと心地よさが子どもに穏やかで優しい気持ちを与え、感情を落ち着かせてくれます。心のお友達として永く付き合っていくことができますよ。
ウォルドルフ人形は手作りが基本です。
子どものことを思いながら作り上げられた人形は、子どもにも作り手にも大切な存在になるからです。
知らない人の手作りより、ママやパパが作ってくれたもののほうが特別感がありますものね。
 ちゃみ
ちゃみそうは言っても、大きな人形を作るのって難しそう……
そんな方のために、後ほどご案内するハンドメイドキットが売られています。
それに、手芸が苦手でも大丈夫。“その子のために「時間」と「手」をかけ、「思い」を込めて作る”ことが大切です。
その様子を見た子どもは、自分が愛されている存在として実感できるようになるのです。
ただし、人形を作る過程は子どもにとっては刺激が強いかもしれません。
人形の体に針を刺して縫う光景が、さながら縫合手術のようだからです。
針で目を刺したり、糸で首を絞めたり……自分が怖いと思うことは見せたくないですよね。
というわけで、手足がついた人形の本体は、子どもが見ていないところで作ることが望ましいようです。
ウォルドルフ人形は手作りが推奨されていますが、もちろん既製品を購入してもOK。
年齢別に、おすすめのウォルドルフ人形を紹介します。
ウォルドルフ人形は、0歳から遊び始めることができます。特に、最初の人形としておすすめなのが「ブランケットドール(Blanket Doll)」です。
ブランケットドールは「タオルドール」とも呼ばれ、その名の通り、ブランケットと人形を組み合わせたようなデザインが特徴です。
形のない柔らかい体と、四隅に縫い付けられたシンプルな手足があり、手足は赤ちゃんが噛んだり握ったりするのに適しています。
ブランケットドールで一番有名なのがナンヒェンというブランドのものですが、日本だとなかなか同じものが売られていません。
楽天ではシュタイナーのおもちゃを扱うお店で、デンマークのネイチャーズーというブランドのブランケットドールが売られています。ぜひチェックしてみてください。
2~3歳になると「人形」という概念をより理解しやすくなります。この年齢の子どもには、抱き人形をおすすめします。
このタイプのウォルドルフ人形は、抱きしめたりぎゅっと握ったりしやすいデザインが特徴。
体は枕のように柔らかく、幼い子どもが安心して抱きしめたり掴んだりできます。
手足は小さな子どもが口に入れたくなるような形になっていますが(笑)、ブランケットドールと同様に安全な素材で作られています。
ナンヒェンのプチベビー、リトルベビー、ベビー、ナチュラルベビー(日本販売品、大きさ小さい順)などがあります。
-こげ茶髪.webp)
4歳以上の子どもには、クラシックなウォルドルフ人形がおすすめです。この年齢の子どもたちは、想像力を駆使して遊び始めるため、よりリアルな人形が最適です。
クラシックなウォルドルフ人形は、柔軟な腕と脚を持ち、さまざまなポーズをとらせたり、服を着せ替えたりすることができます。
女の子の人形はトレードマークである長い髪が特徴で、自由に編み込んだりスタイリングすることができます。
-こげ茶髪の顔.webp)
-こげ茶髪の足.webp)
4歳頃になると、ままごと遊びに夢中になる子が多いですよね。
ウォルドルフ人形には服を着せたり、ごはんを食べさせたり、一緒にお茶会を開いたりと、さまざまなシチュエーションで楽しむことができる魅力がいっぱいです。
また髪の毛が生えているので、おしゃれをさせたりする楽しさも加わり、最高の遊び相手となるでしょう。
クラシックなウォルドルフ人形として有名なのが、ケーセン社で作られているジルケ人形です。
性別、紙の色、肌、服がちがうものがたくさんありますので、ぜひお気に入りの子を見つけてみてください。
 ちゃみ
ちゃみ我が家には、ジルケ人形・Emma(エマ) こげ茶髪がいます♪
次でご紹介する手作りキットもおすすめです。
手作りすることも重要とされているウォルドルフ人形。ここでは、作り方の本とキット、参考サイトをご紹介します。
基本事項として、クラシックなタイプの大きさは4種類あり、小さい方からA体、B体、C体、D体となっています。
大きさが異なるだけで、作り方にはほとんど差異はありません。
小さいほど細かい作業がありますし、大きいほどパーツをつなぎ合わせるのに力が要る印象です。
作り方の本
作成キット
お人形のお店や木のおもちゃ屋さんがキットを販売しています。
こんな順番で作ります。
詳しくは、解説サイトをご参照ください。写真付きで丁寧な解説をされています。
ウォルドルフ人形を子どもに与えるとき、まずは大人が人形に愛情をもって接する姿を見せましょう。
子どもは大人の姿を見て模倣するもの。大人が人形を大切にすることで、子どもとの橋渡しをすることができます。
遊び方については教えることはしません。
なぜなら、子どもが想像力を働かせて自由に遊ぶこと(オープンエンドな遊び)がウォルドルフ人形の目的だからです。
まだ小さいうちは初めてのお友達として、触ったり抱きしめたりして遊びます。
自然素材で出来ているので安心して触らせてあげられますよ。
 ちいくまちゃん
ちいくまちゃん柔らかくてぎゅっとすると気持ちが良いね!
汚れても洗えるところが良いですよね。
2歳を過ぎたころになると、自然と妹や弟のようにお世話をするようになります。
お着替えをさせてみたり、おんぶしてみたり、おままごとに参加させてみたり。
それぞれの楽しみ方で人形と遊ぶのです。
人形と関わる子どもの遊びの様子をよく見ることで、その子の成長を知れるという楽しみにもなりますね。

人形遊びというと、女の子の遊びというイメージがありますが、女の子だけに限定されるものではありません。
男の子にとっても「心のお友達」として、一緒に遊べる存在になるんです。
性別を問わず、お世話をしてあげるという行為を通して他者への思いやりや、年長者としてのふるまいを身につけることができます。
ひいては責任感やリーダーシップといった、将来きっと役立つ力も身につけられるのです。
ましてやウォルドルフ人形は、パパやママが自分のために作ってくれた世界で「一人」のお人形さん。
子どもたちの素敵な心を育んでくれるはずですよ。
シュタイナー関連記事

参考文献:『シュタイナー教育 おもちゃと遊び』

この記事が気に入ったら
フォローしてね!
コメント